用語集
- [更新日:]
- ID:29
ア
アーチ式コンクリートダム(アーチシキコンクリートダム)
コンクリートダムの一種で、主としてアーチ作用により加重を伝達する構造のダム。重力式ダムに比べて小さな提体積で設計でき、経済的に有利である。
アスファルト混合物(アスファルトコンゴウブツ)
所定の粒度の骨材とアスファルトを適度な配合で混合したもの。主にアスファルト舗装に用いられる。
アルカリ度(アルカリド)
水中に含まれる炭酸水素塩。中和するのに必要な酸の量に相当するアルカリ量を炭酸カルシウムのmg/Lで表したもの。
安定水源(アンテイスイゲン)
河川において水源施設の整備などにより、年間を通じて安定的に水量が確保される水源。
イ
育苗土(イクビョウド)
水稲の苗を育てるときに使用する土のこと。
一系(イチケイ)
御所浄水場において、下渕頭首工右岸で取水し、農業用水とともに大和平野導水路から浄水場へ導水し、浄水処理する系統。
ウ
右岸(ウガン)
河川の上流から下流を見たときの右側の岸。
宇陀川系(ウダガワケイ)
室生ダムを水源とし、桜井浄水場で浄水処理を行って送水される系統。桜井系とも言う。
宇陀川系統(ウダガワケイトウ)
室生ダムを水源とし、桜井浄水場で浄水処理を行って送水される系統。桜井系統とも言う。
エ
営業外収益(エイギョウガイシュウエキ)
預貯金、貸付金から生じる受取利息、有価証券の配当、損失補てん的な意味をもつ補助金等で、主たる営業活動以外の原因から生じる収益。
営業外費用(エイギョウガイヒヨウ)
借入金の支払利息等、主たる事業活動以外の原因から生じる費用。
営業収益(エイギョウシュウエキ)
主たる営業活動から生じる収益。水道事業における給水収益等。
営業損失(エイギョウソンシツ)
営業収益から営業費用を差し引いた残額。主たる営業活動から生じる利益または損失。プラスの場合は営業利益、マイナスの場合は営業損失。
営業費用(エイギョウヒヨウ)
主たる事業活動から生じる費用。原水費、減価償却費、人件費等。
営業利益(エイギョウリエキ)
営業収益から営業費用を差し引いた残額。主たる営業活動から生じる利益または損失。プラスの場合は営業利益、マイナスの場合は営業損失。
遠隔制御(エンカクセイギョ)
離れた場所から制御を行うこと。
遠隔操作(エンカクソウサ)
離れた場所から操作を行うこと。
オ
オープンカット工法(オープンカットコウホウ)
地表面から掘削して、水道管を埋設する工法。開削工法とも言う。
カ
加圧脱水機(カアツダッスイキ)
浄水で出る土砂には水分が多く含まれているため、これに機械的圧力を加え、圧さく、脱水する装置。
開削工法(カイサクコウホウ)
地上より直接土砂を掘削して、水道管を埋めていく工法。オープンカット工法とも言う。
拡張事業(カクチョウジギョウ)
水需要の増大等にともない、水源や施設を拡張し、給水能力を高めるための事業。
苛性ソーダ(カセイソーダ)
水酸化ナトリウムのこと。凝集処理などで凝集補助剤として使用する。
渇水(カッスイ)
異常な少雨によって、河川を流れる水が減少し、水需要に対して供給が一時的に不足した状態。
渇水対策本部(カッスイタイサクホンブ)
渇水になった場合に渇水対策を行うために設置される組織。県渇水対策本部と水道局渇水対策本部がある。
活性炭(カッセイタン)
表面に非常に小さな穴が無数にある炭素の物質で、表面積が極めて大きいため、有機物質の吸着力にすぐれている。形状から、粉末活性炭と粒状活性炭に分けられ、浄水の高度処理に利用される。
かんがい(カンガイ)
田畑に水を補給し、土地を潤すこと。
管廊(カンロウ)
浄水場内の配管などを設置している点検通路。維持管理に必要な空間を有している。
キ
企業債(キギョウサイ)
国や公営企業金融公庫や企業から借り入れた借金。
企業債償還金(キギョウサイショウカンキン)
国や公営企業金融公庫等に借入した借金の元金。
給水(キュウスイ)
給水申込者に対して、必要な量の飲み水を供給すること。
給水区域(キュウスイクイキ)
水道事業者が一般の需要に応じて給水を行うことのできる区域。なお、給水区域を広げる場合には、厚生労働大臣(都道府県知事)の認可を受る必要がある。
水道事業者は、この区域内において給水の義務を負う。
給水制限(キュウスイセイゲン)
渇水時において、ダムから水を引く量を減らし、市町村に送る水の量を制限すること。制限は水源状況を考慮しながら、段階的に行う。
急速ろ過(キュウソクロカ)
原水を薬品により凝集沈でん処理したのち、急速ろ過池でろ過し、塩素消毒を行う浄水方式。
幅広い原水処理が可能となるが、緩速ろ過に比べて処理操作に技術が必要となる。
急速ろ過池(キュウソクロカチ)
急速ろ過方式において、ろ過に使用するろ過池。
緊急遮断弁(キンキュウシャダンベン)
地震や水道管の破裂などの異常を感知すると、自動的に緊急閉止できる機能を持ったバルブ。貯水槽などに緊急遮断弁を設置すれば、地震時などに水道管が破裂した場合でも、貯水槽の水を逃がすことなく緊急用水として用いることができる。奈良県水道局では、耐震浄水池などに緊急遮断弁を設置し、緊急用水が確保できるようにしている。
ケ
傾斜板(ケイシャバン)
沈でん池に、沈降面積を増やし処理能力を向上させるために設置する傾斜した板。沈でん能力が向上する。桜井浄水場および御所浄水場の2系の沈でん池に傾斜版がついている。
経常損失・経常利益(ケイジョウソンシツ・ケイジョウリエキ)
経営上生じる正常な収益や費用をいう。主たる営業活動に関する収益と費用(営業収益と営業費用)、主たる営業活動以外の収益と費用(営業外収益と営業外費用)からなる。
減価償却費(ゲンカショウキャクヒ)
固定資産の減価を費用として、その利用各年度に合理的かつ計画的に負担させる会計上の処理または手続によって、特定の年度の費用とされた固定資産の減価額。
原水池(ゲンスイチ)
ダムや河川から取水している場合、原水を貯留しておき、取水不可能な事態が発生したとき緊急に原水を取水できるよう設置される施設。
また、浄水処理では、原水水質の大きな変動は好ましくないが、原水池があればその水質変動を抑えることもできる。
原水調整池ともいう。
原水連絡(ゲンスイレンラク)
渇水や事故等に対応するため、複数の水源を確保し、連絡管等で接続して水運用できるようにすること。県営水道では、御所浄水場において、1系原水と2系原水を場内の連絡管により水融通している。
建設改良費(ケンセツカイリョウヒ)
経営規模の拡充を図るために要する諸施設の建設整備による固定資産の新規取得またはその価値の増加に要する経費。
コ
広域水道事業(コウイキスイドウジギョウ)
市町村の行政区域を越えた広域的見地から経営される水道事業。事業形態には、水道事業と水道用水供給事業とがあり、事業種別では都道府県営と企業団営とがある。
工期(コウキ)
工事を行う期間。
高区浄水池(コウクジョウスイチ)
御所浄水場内にあるpc造の浄水池で、葛城市、香芝市、王寺町、上牧町などへ送水する。
高度浄水処理(コウドジョウスイショリ)
安全でおいしく、安心して飲める水道水をつくるため、通常の浄水処理に追加して導入する処理のこと。
代表的な高度浄水処理の方法として、オゾン処理法、粉末活性炭処理法、生物処理法等があり、これらの処理方法を単独またはいくつか組み合わせで用いる。
御所系(ゴセケイ)
吉野川(大迫ダム、津風呂ダム)を水源とし、御所浄水場で浄水処理を行って送水される系統。吉野川系とも言う。
御所系統(ゴセケイトウ)
吉野川(大迫ダム、津風呂ダム)を水源とし、御所浄水場で浄水処理を行って送水される系統。吉野川系統とも言う。
固定資産(コテイシサン)
土地、建物、機械及び装置等、1年以上にわたって使用される資産。
固定負債(コテイフサイ)
企業債、他団体借入金等、1年以上にわたって返済される負債。
混和池(コンワチ)
凝集剤を原水に一様に混合させるための施設。急速攪拌池(きゅうそくかくはんち)、急速混和池とも言う。
サ
砕石(サイセキ)
岩石を人工的に砕いてつくったもの。セメントコンクリートやアスファルトコンクリートの骨材などに利用される。
サイフォン(サイフォン)
管内の水は両端の落差によって流れるので、この原理を利用して高い場所を越えて送水することをいう。
左岸(サガン)
河川の上流から下流を見たときの左側の岸。
桜井系(サクライケイ)
室生ダムを水源とし、桜井浄水場で浄水処理を行って送水される系統。宇陀川系とも言う。
桜井系統(サクライケイトウ)
室生ダムを水源とし、桜井浄水場で浄水処理を行って送水される系統。宇陀川系統とも言う。
暫定水利権(ザンテイスイリケン)
水源が安定的に確保されていない状況の中で、水需要の増大から緊急的な取水が必要となった場合に、許可期限を定めて取水を可能とする水利権。
サンプリング(サンプリング)
原水や浄水の水質を監視するため、水質検査用に水を採水すること。
残留塩素(ザンリュウエンソ)
水中に塩素を注入することによって水中に残留した有効塩素のこと。遊離残留塩素と結合残留塩素に区分される。
衛生上の措置として給水栓の遊離残留塩素の場合、0.1mg/L以上保持するよう規定されている。
シ
シールド工法(シールドコウホウ)
「シールド」と呼ばれるトンネル掘削機で地中を掘削しながら、セグメントと呼ばれる覆工体を用いてトンネルを構築する工法。地中深く、もぐらのようにトンネルを掘ることができる。
シールドトンネル(シールドトンネル)
シールド工法によって構築されたトンネル。
シールドマシン(シールドマシン)
シールド工法に用いるトンネル掘削機のこと。掘削する地盤の土質によって全面開放型、部分開放型、密閉型(泥水式、土圧式)に分類される。
時間給水(ジカンキュウスイ)
渇水により一日24時間の給水が確保できず、決まった時間帯にのみ給水を行う状態。
色度(シキド)
水中に含まれる溶解性物質およびコロイド性物質が呈する黄褐色の程度をいう。水道水質基準「5度以下であること」とされている。
試験湛水(シケンタンスイ)
ダムが完成した後に、ダム本体や基礎地盤、貯水池周辺等の安全性を確認するため、一定速度でダムに試験的に水を貯留すること。
資産(シサン)
奈良県広域水道企業団の経営の活動手段である財産の運用形態を示すもの。土地、建物現金等。
施設管理台帳(シセツカンリダイチョウ)
県営水道が水道施設の適切な維持管理を行うため作成した台帳システムで水道管理支援システムの一部。施設管理台帳、弁室台帳、水管橋台帳、機械台帳等がある。
自然流下(シゼンリュウカ)
位置エネルギーを利用して水を流下させる方式。ポンプ圧送方式に対する用語。
支払利息(シハライリソク)
営業外費用の1つで、企業債、他会計からの借入金、一時借入金等に対して支払う利息をいう。
資本(シホン)
奈良県広域水道企業団の総資産額から総負債額を差し引いた残額、つまり、支払うべき額を差し引いた自身に帰属する財産の額を示すもの。(ただし、建設改良のために起こす企業債や他会計借入金を含む)。
資本金(シホンキン)
増殖の目的をもって事業に投下した資金。出資金や組入資本金等からなる。
修繕費(シュウゼンヒ)
増殖の目的をもって事業に投下した資金。出資金や組入資本金等からなる。
重力式コンクリートダム(ジュウリョクシキコンクリートダム)
コンクリートダムの一種で、提体の自重で荷重に抵抗する構造のダム。アーチ式ダムに比べてダム体積が大きいため、建設費が高く工期が長くなる欠点がある。
取水(シュスイ)
ダムや河川、地下水等から取水施設を使い原水を取り入れること。
受水市町村(ジュスイシチョウソン)
奈良県広域水道企業団が用水供給している市町村のこと。現在、2市。
取水制限(シュスイセイゲン)
渇水によりダム貯水池等の貯水量や河川流量が低下し、河川管理者が取水量を制限すること。
受水地(ジュスイチ)
受水市町村が県営水道の水を受水している地点。市町村水道事業体の浄水場や配水タンクなどが受水地点となっている。
取水塔(シュスイトウ)
ダムなどの貯水池から取水するために設けられた塔状の構造物。取水塔は水温や水質などの影響を考慮しながら、水深によって選択して取水することができる。
浄水池(ジョウスイチ)
浄水場内において、浄水処理や事故時などの水量変動に対応するために浄水を貯留する池。
情報伝送設備(ジョウホウデンソウセツビ)
さまざまな情報をコンピューターシステムで処理して通信回線を介して送信するための設備。
剰余金(ジョウヨキン)
奈良県広域水道企業団がもうけ等の中から蓄積してきた金額。毎事業年度の利益を積み立てた利益剰余金と、国庫補助金等を積み立てた資本剰余金からなる。
人件費(ジンケンヒ)
水道事業に従事する職員の給料や手当等の費用。
ス
水源涵養(スイゲンカンヨウ)
森林が降雨を貯留する天然の水源としての機能をもつこと。
水源保全(スイゲンホゼン)
水道の原水を供給する水源を守り、水道水源の水質を保全すること。
推進工法(スイシンコウホウ)
発進立坑に設置したジャッキの推進力で管体を押し込んで水道管を布設する工法。
水道事業(スイドウジギョウ)
一般の需要に応じて、計画給水人口が100人を越える水道により水を供給する事業。特に、計画給水人口が5000人以下である場合は簡易水道事業(簡水)、5000人超の場合は上水道事業(上水)と呼ばれる。
水道用水供給事業(スイドウヨウスイキョウキュウジギョウ)
水道事業者に水道水を供給する事業。すなわち水道用水供給事業は水道水の卸売業である。
水理計算(スイリケイサン)
水理学に基づき、浄水場や送水管路の有効水頭を計算すること。
水利権(スイリケン)
河川の水を排他的、継続的に使用する権利。河川法の規定により河川から取水することを認められた権利。
スラッジ(スラッジ)
水中の濁質(浮遊土)が沈降した泥状のもの。浄水処理において発生する。
セ
前年度繰越利益剰余金(ゼンネンドクリコシリエキジョウヨキン)
前期から処分されないで繰り越されてきた利益(または損失)。
占用(センヨウ)
道路や河川など公共物の地下に、関連法に基づき水道管やガス管などの公共物を埋設すること。
ソ
送水(ソウスイ)
浄水場できれいにした水を配水池などへ水道管で送ること。
損益勘定留保資金(ソンエキカンジョウリュウホシキン)
現金支出を伴わない減価償却費や資産減耗費など、企業の内部に留保される資金。資本的収入が支出に対して不足する場合の補てん財源になる。
損益計算書(ソンエキケイサンショ)
一事業年度における事業活動の経営成績を明らかにするもの。(収益-費用=利益)として表示される。
タ
貸借対照表(タイシャクタイショウヒョウ)
ある一定の時点において保有するすべての資産、負債等の財政状態を総括的に表した報告書。バランスシートとも言う。
耐震浄水池(タイシンジョウスイチ)
地震に対する安全性を確保するよう配慮して設計された浄水池。
太陽光発電(タイヨウコウハツデン)
太陽光エネルギーを太陽電池により、二酸化炭素を発生させることなく電気エネルギーに変換する発電システム。
濁度(ダクド)
水の濁りの程度。精製水1リットル中に標準カオリン1mgを含むときの濁りに相当するものを1度としている。
水質基準は「2度以下であること」とされている。
脱水ケーキ(ダッスイケーキ)
浄水場から排出するスラッジの処分を容易にするために脱水されたケーキ。脱水スラッジともいう。
ダムサイト(ダムサイト)
ダム提体を建設するための敷地、用地のこと。
チ
地下埋設物協議(チカマイセツブツキョウギ)
道路掘削工事等を行う場合に、上下水道管、ガス管、通信ケーブル等の地面下に埋設されている施設について、その管理者と協議を行うこと。
着水井(チャクスイセイ)
浄水場に流入する原水の水位を安定させ、水位調節と流入量測定を行うために設けられた池。
中塩(チュウエン)
砂ろ過前の沈でん水に塩素を注入する方法をいい、中間塩素処理、中塩素とも呼ばれる。この方法はトリハロメタンの低減化に有効である。
調整池(チョウセイチ)
水道用水供給事業体において、送水量の調整や異常時の対応のため浄水を貯留する池。送水施設の一部であり、送水施設の途中または末端に設置される。
沈砂池(チンサチ)
取水施設により河川表流水を取水して、原水とともに流入した砂などを沈降除去するための施設。
沈でん池(チンデンチ)
水よりも重い粒子は清水中やきわめて静かな流れの中では沈降して水と分離する。この原理を利用して、原水を静かに流れる広い池に流入させて原水中の粒子を分離する池を沈でん池と呼ぶ。
テ
低区浄水池(テイクジョウスイチ)
御所浄水場内にあるRC造の浄水池の一つで、大和高田市や橿原市、奈良市、大和郡山市などへ送水する。
テレメーター(テレメーター)
遠方に設置された施設および設備機器(テレメーター)を制御所から遠方監視および操作設備によって監視制御すること。テレメーメータ・テレコントロール(遠方監視制御)とも言う。
ト
当期損失・当期利益(トウキソンシツ・トウキリエキ)
その年度の最終の利益または損失をいう。純利益または純損失。
投資(トウシ)
企業が1年を超えて、利益を得る目的で、事業などに資金を出したり貸し付けている資産をいう。
頭首工(トウシュコウ)
河川などから主としてかんがい用水を取水するために、幹線水路の頭部に設けられら取水施設の一種で、堰、取水門、などの付帯施設の総称。水道関係では取水堰にあたる。
導水(ドウスイ)
原水を取水施設から浄水場まで送ること。
導電率(ドウデンリツ)
電気伝導率とも言う。断面積1平方センチメートル、距離1cmの相対する電極間にある溶液の伝導度をいう。水質基準項目ではないが、浄水処理などで有効な水質指標となっている。
当年度未処理欠損金(トウネンドミショリケッソンキン)
前年度繰越利益剰余金(または繰越欠損金)に当年度の純利益(または純損失)を加減した後、損失が出た場合の額。
当年度未処分利益剰余金(トウネンドミショブンリエキジョウヨキン)
前年度繰越利益剰余金(または繰越欠損金)に当年度の純利益(または純損失)を加減した後、利益が出た場合の額。
動力費(ドウリョクヒ)
機械装置等の運転に必要な電力料や燃料費。
特別高圧(トクベツコウアツ)
水道施設等で受電する場合に、7000Vを超えるもの。
特別損失・特別利益(トクベツソンシツ・トクベツリエキ)
経営上生じる異常な、臨時の損失や利益。災害損失や土地売却益(売却損)などがその具体的な例である。
ニ
二系(ニケイ)
御所浄水場において、下渕頭首工左岸から取水し、水道専用導水路から浄水場へ導水し、浄水処理する系統。御所浄水場の拡張事業により整備された。
N(ニュートン)
力のSI単位系の単位。1N=kgm/S2。重力単位系ではkgf。
ノ
濃縮槽(ノウシュクソウ)
排泥池から送られたスラッジの濃度を自然沈降、機械による遠心力などによって高めること目的とした施設。
ハ
配水(ハイスイ)
浄水場でつくられた水を安全かつ円滑に需要者に輸送すること。
排水処理施設(ハイスイショリシセツ)
浄水処理工程から排出される沈降スラッジや、ろ過池の洗浄排水を濃縮、脱水、乾燥などにより処理する施設。処理方式には、天日乾燥方式、加圧脱水方式、凍結融解方式などがある。
排水池(ハイスイチ)
ろ過池洗浄排水などの固液分離の効率をよくするための排水処理施設。
配水池(ハイスイチ)
給水区域の需要量に応じて適切な配水行うため、浄水を一時的に蓄える池。
排泥池(ハイデイチ)
沈でん池の排泥または沈でん池の排泥とろ過池の洗浄排水の両方を受け入れ、一時的に貯留する池。
pa(パスカル)
圧力のSI単位系の単位。1pa=1N/平方メートル。重力単位系ではkgf/平方メートル。
フ
負債(フサイ)
奈良県広域水道企業団外部への返済を要するマイナスの財産。借入金や未払金等からなる。
フロック(フロック)
凝集剤の注入により原水中の濁質は荷電が中和されて反発力を失い、マイクロフロックを生じ、さらに凝集剤の水和によって大型の粒子魂を生じる。フワフワしていて綿毛に似ているのでフロックと呼ばれる。
フロック形成池(フロックケイセイチ)
沈でん池の前処理としてフロック形成を行う池。フロックを成長させるための緩速攪拌を行い、機械攪拌方式と迂流方式とがある。
粉末活性炭(フンマツカッセイタン)
表面に非常に小さな穴が無数にある炭素の物質で、表面積が極めて大きいために、有機物質の吸着力にすぐれている。形状から、粉末活性炭と粒状活性炭に分けられ、浄水の高度処理に利用される。
ヘ
弁室(ベンシツ)
バルブを設置してある箱形の構造物、ボックスなど。
ホ
豊水(ホウスイ)
例年より降水量が多いこと。10年に1回程度の確率で発生する降水量の多い年を豊水年という。
ポンプ場(ポンプジョウ)
地形、構造物の立地または管路の状況など、諸条件に応じたポンプ圧送方式により水を送る設備を設置した場所。
ミ
水資源機構(ミズシゲンキコウ)
水資源開発促進法の規定による水資源開発基本計画に基づく水資源開発を行う独立行政法人。旧水資源開発公団。
水融通(ミズユウズウ)
渇水や災害時に、水源の複数化、幹線管路の相互連絡などによって水を効率的に運用すること。
ム
無薬注加圧脱水(ムヤクチュウカアツダッスイ)
スラッジを脱水する際に、石灰や高分子凝集剤を使わずに加圧だけで脱水すること。
メ
Mpa(メガパスカル)
圧力のSI単位系の単位。1Mpa=106N/平方メートル。重力単位系では106kgf/平方メートル。
モ
目標年度(モクヒョウネンド)
水道施設の規模を決める上で、水源確保や施設整備の目標とする年度。
ヨ
用水供給(ヨウスイキョウキュウ)
水道により、水道事業者にその用水を供給することで、すなわち水道用水供給事業は水道水の卸売業である。
揚程(ヨウテイ)
ポンプが単位時間に流れる液体に対して与えるエネルギーを水頭で表したもの。
吉野川系(ヨシノガワケイ)
吉野川(大迫ダム、津風呂ダム)を水源とし、御所浄水場で浄水処理を行って送水される系統。御所系とも言う。
吉野川系統(ヨシノガワケイトウ)
吉野川(大迫ダム、津風呂ダム)を水源とし、御所浄水場で浄水処理を行って送水される系統。御所系統とも言う。
リ
粒状活性炭(リュウジョウカッセイタン)
表面に非常に小さな穴が無数にある炭素の物質で、表面積が極めて大きいために、有機物質の吸着力にすぐれている。形状から、粉末活性炭と粒状活性炭に分けられ、浄水の高度処理に利用される。
流量計(リュウリョウケイ)
単位時間に流れる気体や液体の体積を測る容積流量計と流速を測って間接的に求める瞬時流量計とに大別される。容積流量計にはガスメーター、水道メーターなどがある。瞬時流量計には、電磁流量計、超音波流量計などがある。
量水器(リョウスイキ)
給水装置に取り付け、需要者に対する水量を積算計算するための計量器。水道メーターのこと。
流動資産(リュウドウシサン)
現金預金、未収金等、1年以内に使用される資産。
流動負債(リュウドウフサイ)
一時借入金、未払金等、1年以内に返済される負債。
ロ
漏水事故(ロウスイジコ)
給水管などの老朽化、腐食、施工不良などにより水道水が地上や地下に漏れ出すこと。
このページに関するお問い合わせ先
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
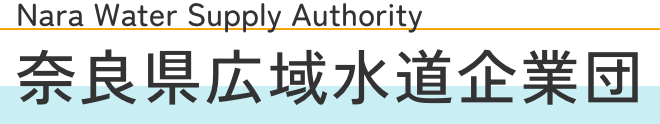
 検索
検索